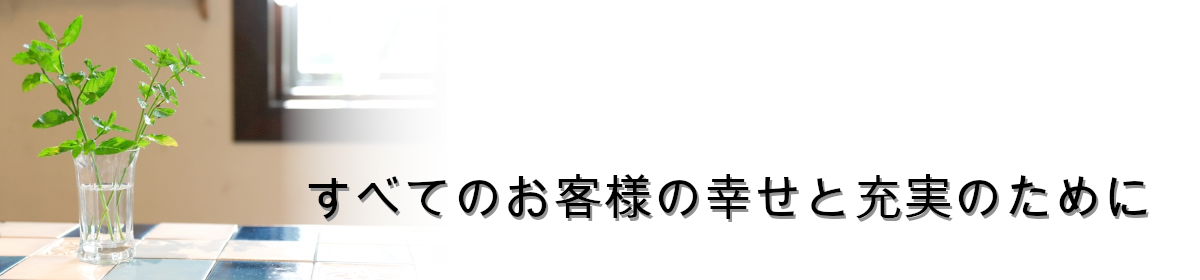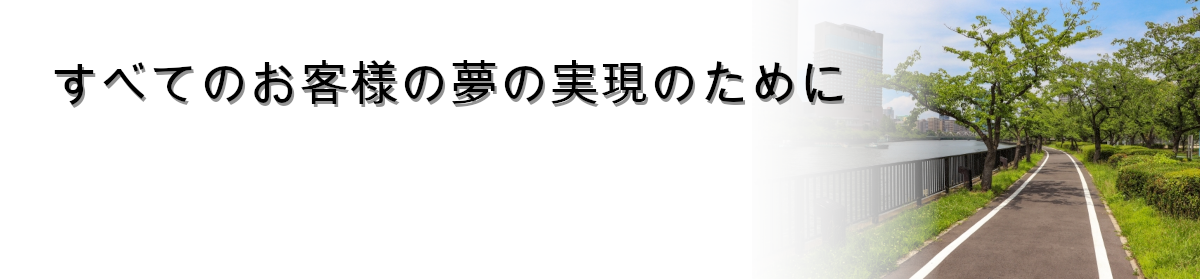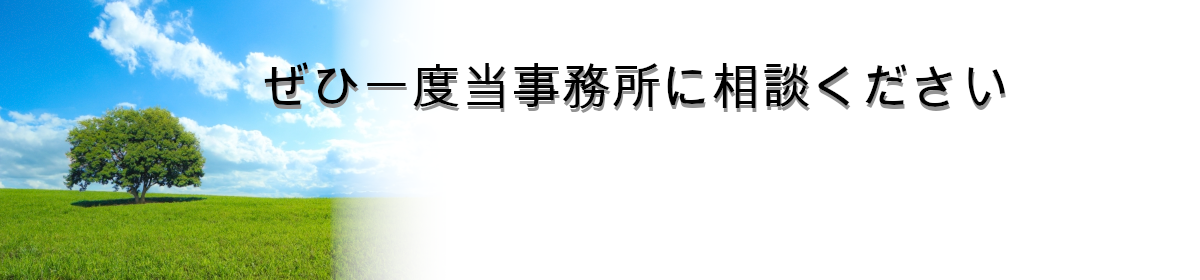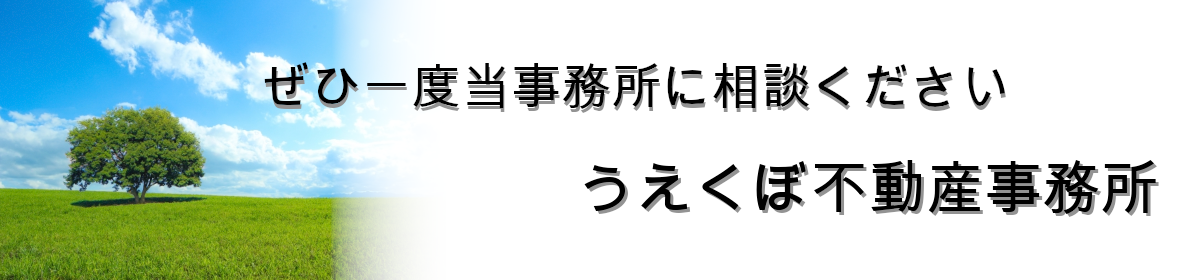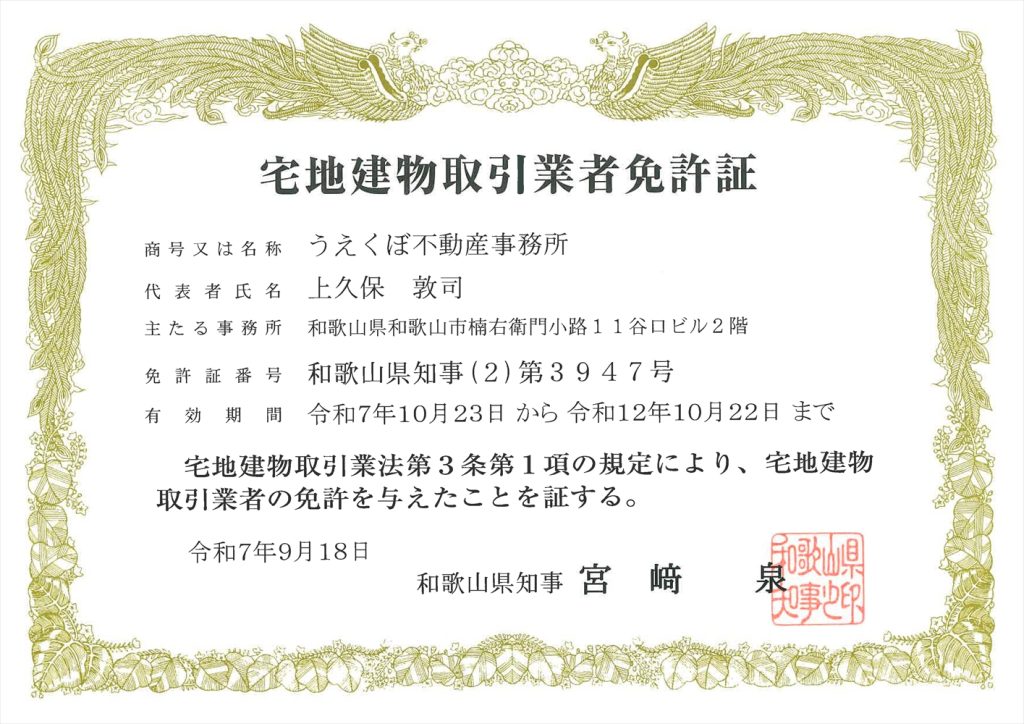1.Q:中古住宅を買う契約をしました。しかしやっぱり単純に物件が気に入らなくなったので契約を解除したいと思いますができますか?
A:契約後、気に入らない点があるからといって契約を解除するのであれば、原則として契約の定めに従う必要があります。媒介(仲介)業者の説明に不備があり重要事項説明が正しく行われていない場合等には、媒介(仲介)業者の責任を追及できますが、手付金を放棄する等して解除することになると思われます。重要事項説明や契約説明の際には、わからない点については十分に確認することが必要です。その上で「買うか、買わないか」の判断を行い、契約を締結するものです。なお、契約の解除・取消しには、法律の規定に基づいた解除【(1)クーリング・オフ制度・(2)契約違反による解除・(3)契約不適合責任による解除・(4)消費者契約法による契約の取消し】、手付放棄による解除、話合いによる契約の解除(合意解除)、錯誤や詐欺による契約の取消し等があります。
2.Q:2項道路(ニコウドウロ)とはどういう道路ですか?
A:建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。
3.Q:不動産の公簿売買とはなんですか?
A;公簿売買とは、売買契約に当たり、土地・建物の登記簿の表示面積により売買代金を確定し、後に実測した面積との間で差が生じても代金を清算しない契約方式のことをいいます。これに対して、実測面積により売買代金を確定させる契約方式を実測売買といいます。本件の取引が実際に公簿売買であったかどうかは売買契約書の条項により確認することになるでしょう。なお、売主が数量を指示して売買した(一定の面積があることを売主が契約において表示し、その数量を基準にして売買代金が算出された)場合に、その数量が不足し、買主がその不足を知らなかったときには、契約不適合責任により買主は追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除(残存部分だけなら買わなかったであろうとき)ができます(民法565条等)。また、売買契約書に「すべて面積は公簿による」との条項があった事案で、買主が実測面積に関心を持っていたことが認定されて、公簿面積より5%強小さかった土地について、売買契約の6年後に代金の減額請求が認められた事例(最判平成13年11月22日)があります。
4.Q:不動産業者から新築住宅を購入しました。先日の台風で雨漏りが見つかったのですが、売主の不動産業者に責任追及ができますか。
A: 新築住宅の場合、「住宅の品質確保と促進等に関する法律」(略称:品確法)により、売主は、引渡しの日から10年間、住宅の基本構造部分(住宅の構造耐力に主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの)について、責任を負うことが義務付けられています。よって購入したばかりの住宅の雨漏りは、その台風がこれまでの想定を越える様なものでない限り、宅建業者である売主に補修等の請求ができます。
5.Q:不動産の購入申込みを行い、申込金を支払いましたが、こちらの都合でキャンセルをしたいと考えています、 申込金は戻ってくるのでしょうか。
A:宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならないと規定しています(宅建業法47条の2第3項)。購入申込みに際して支払った「申込金」は、物件の購入の意思を示すため等に支払った預り金ですので、自己都合によるキャンセルであっても返還されます。契約の締結前に支払う金銭がある場合は、その金銭を支払う理由と取り扱いについて、 売主や媒介(仲介)業者に確認をしてから支払うように注意しましょう。また、契約後に支払う「手付金」につきましては、自己都合のキャンセルでは多くの場合戻ってきません。
6.Q:自分の家を売る契約をしました。自己都合で契約を解除しなければならなくなりました。契約を解除することはできますか。
A:基本的に当事者間で特段の定めがなければ手付は解約手付とされ、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは買主は「手付放棄」、 売主は「手付倍返し」をして契約の解除をすることができます。売主側は「手付倍返し」による解除となりますが、 買主が「履行の着手」を行っている段階であれば契約条項に従い、契約違反による「違約金」の支払いで解除することができます。
7.Q:新築住宅を購入するため、自宅で物件の説明をするよう頼み、自宅で購入の申し込みをました。3日前に、完成済みのその住宅の中で契約しましたが、やっぱり駅から遠いので解約したくなりました。今ならまだクーリング・オフができますか。
A: いったん契約をしたら消費者であっても原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、特定の取引に限って契約の締結後も一定期間消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができる制度を「クーリング・オフ」といいます。複雑で高額な不動産の取引においても宅建業法37条の2で規定されています。宅建業法では、売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだような場合、宅建業者から書面によるクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、解除通知書面を発信すれば無条件に契約の解除ができます。ただし、買主が、自宅または勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出、そこで申込みあるいは契約をした場合には、無条件で申込みの撤回または売買契約の解除をすることはできないことになっています。今回の場合は、買主の申出により自宅で買受けの申込みが行われているようなので基本的にはクーリング・オフによる契約の解除はできないことになります。
8.Q;土地建物の売買契約をして手付金を支払いました。「契約日から1か月経つと手付解除はできない」という契約になっていますが、こういう契約は有効でしょうか。
A:民法557条1項の手付けの規定は任意規定であり、一定期日を過ぎると手付解除ができないとする手付解除期日の特約を設けることはできます。しかし、売主が宅建業者の場合は、その手付がいかなる性質のものであっても解約手付とみなされ、相手方が履行の着手をするまでは当該契約を手付解除することができます。また、これに反する特約で、買主に不利なものは無効となります(宅建業法39条)。なお、「売主(業者)および買主は、相手方が契約の履行に着手をするまで、または所定の期日までは手付解除できる」旨の特約が付された売買契約が締結された事案で、買主は、売主が履行に着手するまでか所定の期日までのいずれか遅い時期までは手付解除できるとして、売主が所定(手付解除)の期日到来前に「履行に着手」した場合であっても、買主の手付解除を認めた裁判例(名古屋高判平成13年3月29日)があります。つまり、宅建業者が売主で買主が個人の場合は「手付解除期日もしくは履行着手のどちらか遅い方で解除ができる」となり、宅建業者売主で買主が個人の場合以外は「手付解除期日もしくは履行着手どちらか早い方」が解除できる期日なります。
9.Q:「建築条件付土地の売買」とはどういうものですか?
A:土地の売買契約を締結するに当たってその土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。つまり土地を造成した業者がそのまま建物も建築するのでその業者の建物を注文してくださいという契約になります。建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には土地の売買契約は無条件で解除されます。「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点としては、「一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること」、 「請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは本売買契約は解除になること」、「本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと」などが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しておきましょう。
10.Q:ローン特約とは?
A: ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。「ローン特約」を付けるときは、1.融資申込金融機関、2.融資金額、3.融資が承認されるまでの期間、4.融資が承認されなかった場合の対応策、 などの設定を明確にして約定することに注意が必要です。あなたの契約が、「ローン特約条項」によって解除されるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介(仲介)業者は買主に対して手付金を返還するよう促す必要があります。
一覧に戻る