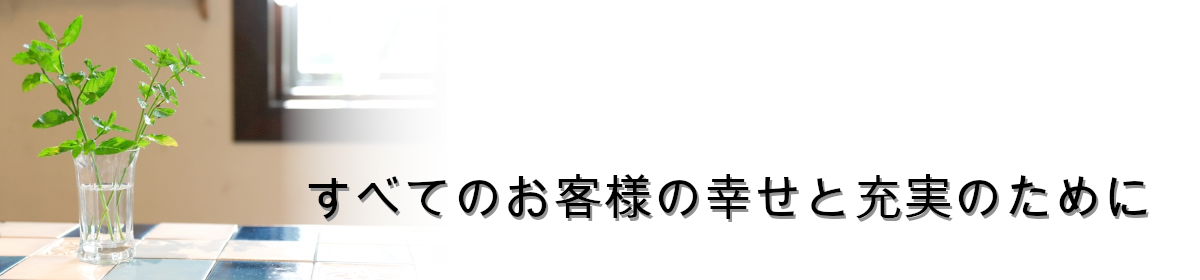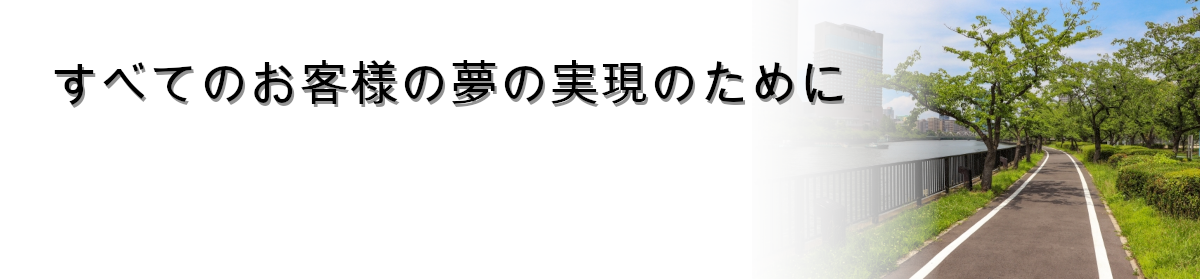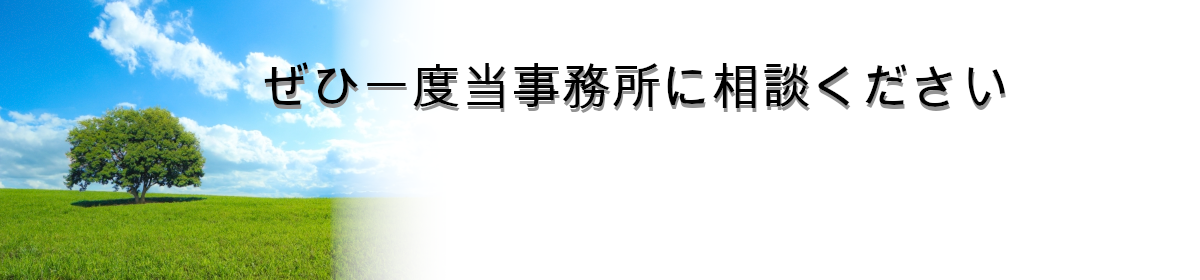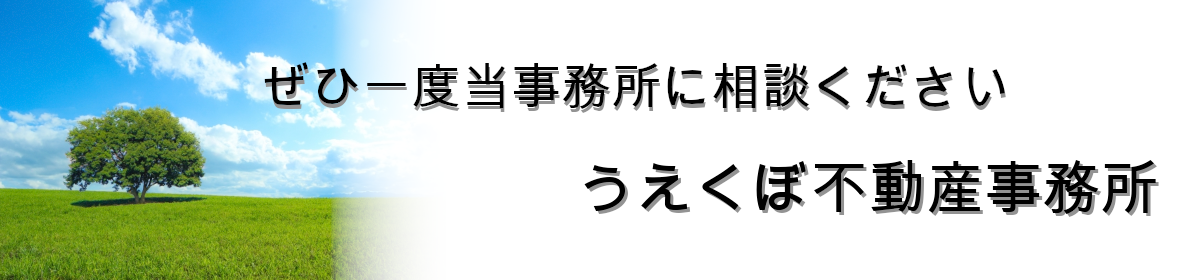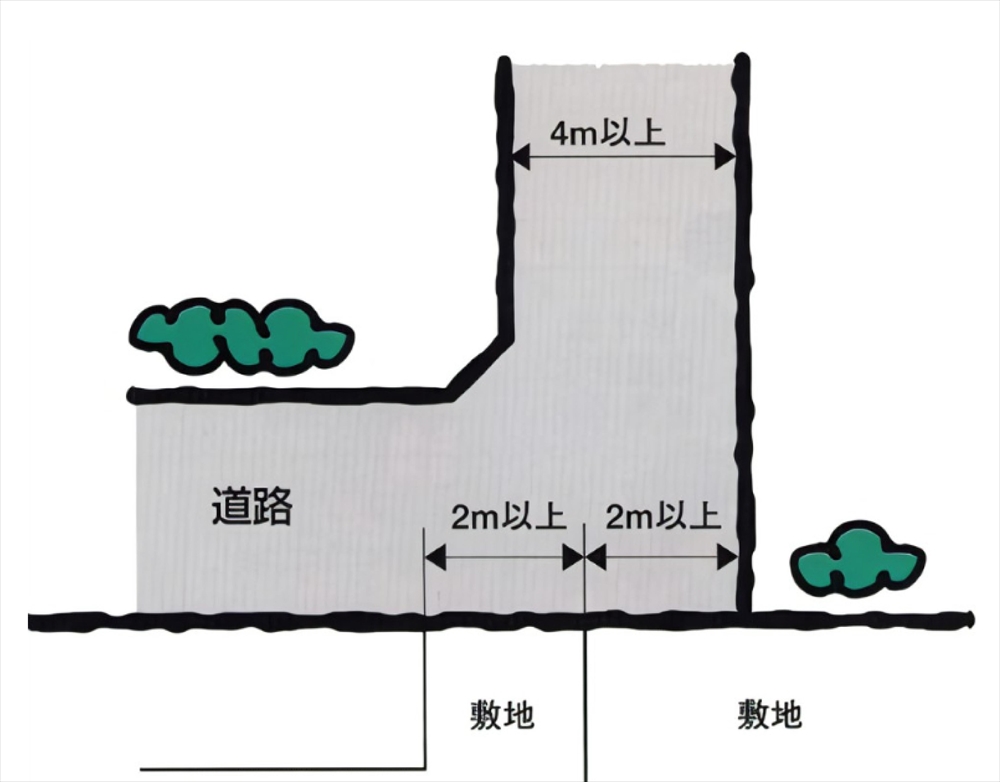★不動産投資とは?
一般の方における不動産投資とは、所有する不動産を貸し出して家賃収入を得る投資のことです。入居者をつけて自らが働くことなく毎月家賃収入を受け取ることが目的です。
不動産投資は意外と難しくありません。不動産を探す際には、不動産会社から紹介してもらいながら探します。また、賃貸管理を管理会社に任せられるため、仕事をしながら副業として不動産投資に取り組めます。
★不動産投資の利益は2種類
不動産投資の利益は、「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」があります。
インカムゲインとは、不動産の所有中に継続して得られる利益のことです。家賃収入や更新料などの、安定的・継続的な利益の事です。
キャピタルゲインとは、不動産の売却によって得られる利益のことです。不動産価格が上昇し、取得時より高い価格で売却できれば、取得価額と売却価額の差額が利益となります。
★投資対象不動産の種類
不動産投資の対象となる主な不動産の種類は以下の通りです。
・一棟マンション
・一棟アパート
・区分マンション
・戸建て
・ビル
・テナント用建物
一棟マンション・アパート・ビルの投資は貸し出せる部屋数が多い分、相対的に大きな利益が期待できます。ただし、不動産価格が高額で、多額の資金が必要になります。
区分マンションの投資は、マンションの1室を貸し出す方法です。一棟物件に比べると価格は低額ですが、戸数が少ない分、一棟物件ほどの大きな利益は期待できなくなります。
また、戸建てを貸し出す方法もあります。戸建てを貸し出す場合、主な入居者としてファミリー層が想定されます。ファミリー層は入居期間が長い傾向にあるため、長期的な安定収入が期待できます。
それぞれの特徴を理解して、投資の対象とする不動産を選びましょう。
★新築と中古の違い
不動産投資は、「新築」と「中古」があります。
新築は建物や設備が新しいので、入居者が見つかりやすく、長く稼働できます。一方で、購入して中古になると、すぐに資産価値が大きく下がるのがデメリットです。
中古は新築より不動産価格が低額ですが、築年数が経過していると、購入後すぐに多額の修繕費がかかることもあるので注意が必要です。
★不動産投資のメリット
不動産投資には、以下のようなメリットがあります。
〇安定収入を得ることができる
不動産投資は、入居者がつくと毎月家賃が得られます。一般的な仕事とは異なり、労働時間や場所などに収入が左右されません。うまく運用できれば、大きな労力をかけることなく安定収入を確保できるでしょう。
〇他人資本を活用できる
不動産投資では、借入金で不動産を取得可能です。また、入居者からの家賃収入でローンを返済できます。まとまった自己資金を準備しなくても、他人資本を活用して効率的に資産を形成できます。
〇労働せずに収入が得られる
不動産投資は、入居者がつけば自らが労働することなく毎月家賃収入を受け取れます。不動産購入後の賃貸管理も管理会社に任せられるため、本業の仕事以外に余分な手間やコストをかけることなく収入を得ることができます。
〇生命保険効果がある
不動産投資で金融機関から融資を受けるときは、「団体信用生命保険(団信)」に加入するのが一般的です。返済中に契約者が死亡した場合は、団信の保険金で残債が弁済されるため、家族にローンのない不動産を残せます。
〇インフレに強い
インフレ(物価上昇)時は、実物資産である不動産の資産価値は下がりにくく、家賃は上昇しやすい傾向にあります。また、物価が上昇しても額面金額は変わらないため、借入金額は実質的に目減りします。これらの特徴から、不動産投資はインフレに強いと言えます。
★不動産投資のデメリット
不動産投資は次のようなデメリットもあります。
〇さまざまな費用がかかる
不動産投資は購入時や所有中、売却時に次のような費用がかかります。
購入時の費用
・仲介手数料
・印紙税
・登録免許税(所有権移転、抵当権設定)
・司法書士費用
・ローン事務手数料
・不動産取得税 など
所有中の費用
・管理費・修繕積立金(※区分マンションの場合)
・業務委託費(※賃貸管理を業者に任せる場合)
・固定資産税所得税・住民税退去時の原状回復費用
・修繕費 など
売却時
・仲介手数料
・印紙税
・登録免許税(抵当権抹消)
・ローン繰上返済手数料
・譲渡所得税(所得税・住民税) など
費用が収入を上回る場合、損失が生じてしまいます。購入時の費用だけでなく、投資期間中にかかる全ての費用も確認し、 収益を確保できるか見極めることが大切です。
★不動産投資のリスクについて
不動産投資にはさまざまなリスクが存在します。「空室リスク」「災害リスク」「流動性リスク」の3つが代表的です。
空室リスクは、入居者が見つからないリスクです。空室期間が長期化すると、ローン返済に支障が出る恐れがあります。
災害リスクは、地震や火事、台風などによって建物が被害を受けるリスクです。空室の長期化、家賃・資産価値の低下を招く恐れがあります。
流動性リスクは、不動産を売却できなくなるリスクです。不動産を売却するには、不動産会社と媒介契約を締結して買い手を見つけなければなりません。なかなか買い手が見つからず、現金化に時間がかかることもあります。
★不動産投資の始め方
「不動産投資を始めたい」と思ったら、次のような流れで手続きを進めましょう。
・十分な 知識を身につける
・不動産会社を探して不動産を紹介してもらう
・売買契約、融資契約、賃貸管理契約を締結する
・入居者を募集し、賃貸借契約を締結する(空室の不動産を購入する場合)
関連書籍やセミナーなどで十分な知識を身につけてから、不動産会社を探して不動産を紹介してもらいます。なぜなら、不動産会社も色々と教えてもらえますが、用語等基礎的なことを学んでいなければ、不動産会社の言っていることが理解できなくて不安になるからです。
不動産が見つかったら売買契約や融資契約を行い、必要に応じて賃貸管理を依頼します。既に入居者がいれば、契約後すぐに家賃収入を得られます。空室の不動産を購入する場合は、入居者募集を行いましょう。
★まとめ
不動産投資は安定収入が期待でき、他人資本を活用して効率的に資産を形成できるのが魅力です。一方で、購入時だけでなく所有中や売却時にも費用がかかり、空室リスク、災害リスク、流動性リスクといったさまざまなリスクも存在します。不動産投資の成功率を高めるためにも、十分な知識を身につけてから不動産投資を始めましょう。