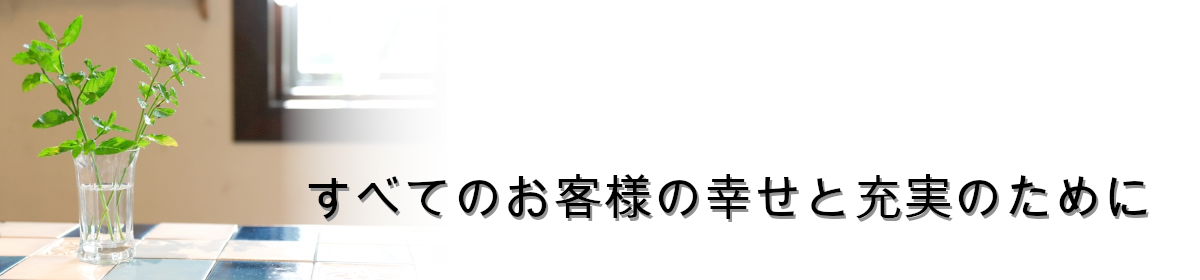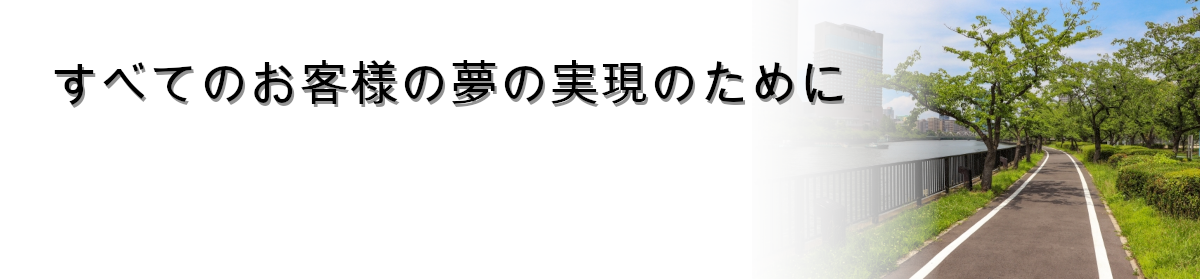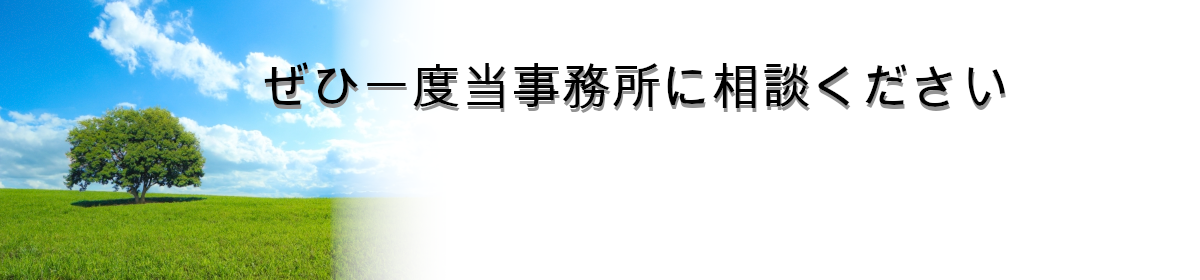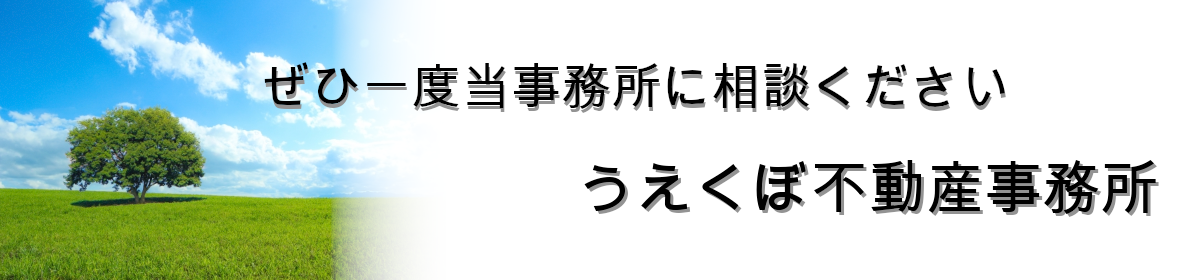1.Q:土地を買って注文住宅を検討していますが、どう進めるとうまくいくでしょうか。
A:まず、土地+建物+諸費用の金額をきめることが大切です。総額の予算が3,000万円で、その内諸費用が200万円、建物価格が1,800万円としますと、土地価格は1,000万円になります。住宅ローンをご利用される場合が殆んどですが、自己資金がある程度用意できれば、ローン返済も楽になります。
2.Q:建築条件付き土地とは何ですか?
A:建築条件無しの土地の場合、建物を建てる建築会社を購入者が自由に選べますが、建築条件付きの土地の場合は、その土地の上に建てる建物の建築会社が指定されます。但し、建築条件付き土地として販売されていても、交渉により建築条件を外せる場合もありますのでお気軽にご質問ください。
3.Q:中古物件を買ってリフォームしたい。どう進めるといいでしょうか。
A;ご購入される物件が決まりましたら、ご契約前にリフォームの見積もりを取られたら良いと思います。そうすれば、物件ご購入後にリフォーム費用がオーバーすることもなく安心です。
4.Q:不動産の売買契約にクーリングオフはあるのですか?
A:ございます。但し、クーリングオフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。
①宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、買主が宅地建物取引業者以外の者であること。
②通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外で、その売買契約が締結された場合。
但し、次の場合は上記1.と2.の条件を満たしていても、クーリングオフができなくなります。
・売主業者が購入申込者(買主)に対して、クーリングオフできる旨を書面告知してから8日以上経過したとき。
・買主が現に物件の引き渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っていたとき。
5.Q:不動産の売買契約をしたけれど、住宅ローンが借りられなかったらどうなりますか。
A:通常、売買契約書には買主が住宅ローンの借入れをすることを記載し、もし融資の承認が得られなかった場合は、買主が売買契約を白紙解約できることを特約に定めます。そうすれば、ローンが借りられなかった場合でも、支払済みの手付金は、買主に全額返金されます。但し、住宅ローンの本申込は、申請書類として売買契約書や重要事項説明書等が必要ですので、契約後でなければローンの本申込ができません。その為、せっかく契約したのに住宅ローンが借りられなかったということにならないように、殆どの金融機関ではローンの事前審査という制度があります。事前審査は、売買契約の締結前に前もって比較的簡略な手続きで、予め、住宅ローンの借入の可否を審査するというものです。住宅ローンを利用される場合には、ローンの事前審査のご利用をお勧めします。
6.Q:重要事項説明書とはどんなものですか?
A:不動産を購入したり借りたりする人に、契約前に、宅地建物取引士が物件について宅地建物取引業法に定められている内容を説明する書類のことです。
7.Q:気に入った物件に、他の人から先に購入申し込みが入ってしまいました。どうすればいいですか。
A:不動産は残念ながら同じものは2つありません。そこで申し込みは基本的に先着順となります。ただし、最初に申し込みをされたお客様が何らかの事情でお申込みをキャンセルされた場合は、2番目に購入申し込みをされたお客様との商談となるのが一般的です。
8.Q;徒歩〇〇分ってどうやって測ったものですか。
A:地図上の道のりを分速80mで歩くと何分かかるかを計算し、端数を切り上げた数値。ただ、徒歩○分はあくまで所要時間の目安。信号や踏切待ちの時間等などは考慮されていないので、最寄駅から現地までは必ず自分の足で歩き、実際の所要時間や交通量、坂道の有無などを確かめましょう。
9.Q:なぜ角地の人気が高いのでしょうか。
A:一定基準を満たした角地は、他の区画より※建ぺい率(※敷地面積に対する建築面積の割合)が10%アップします。また、解放感に優れ、日当たりや採光、通風を確保しやすい事が人気の理由。中でも、東南の角地は東側と南側の日当たりが確保できるので特に人気です。
10.Q:長持ちする家の条件を教えてください。
A:柱や土台にヒノキや鉄骨などの強くて腐りにくい部材を使い、防腐・防蟻処理がしっかり施されていること。雨水の排水処理や床下の換気が良く、湿気の少ないこと。こういったことが建物が長持ちする条件として挙げられます。また、外壁の塗り替えや屋根の葺き替えなど、メンテナンスがしやすいことも大切なポイントです。