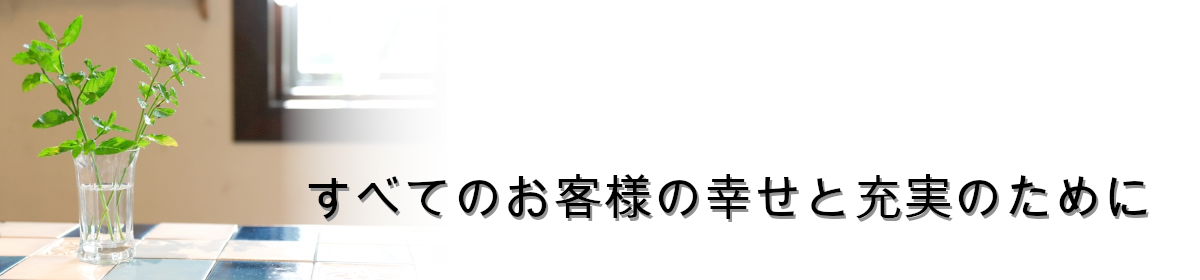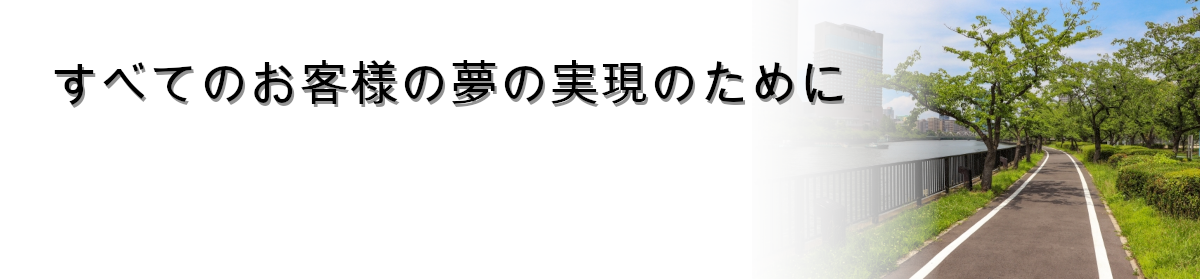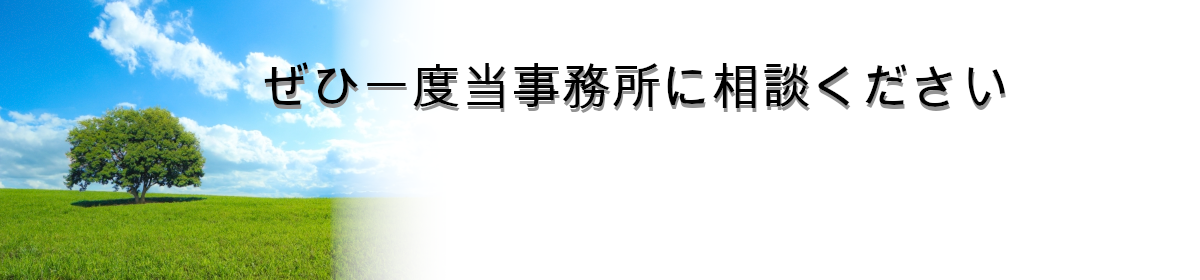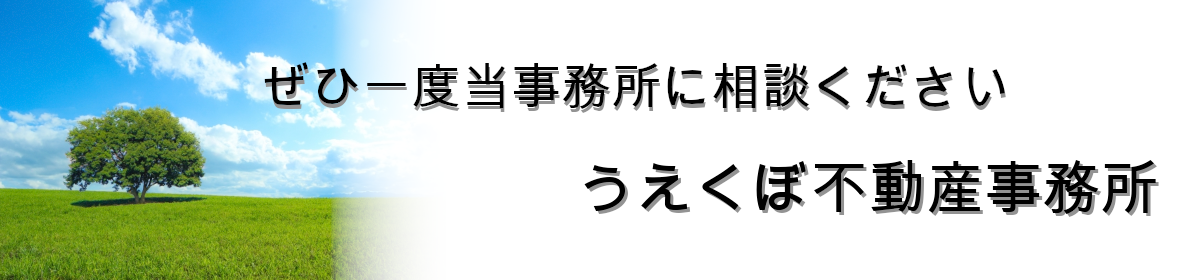狭小地と無接道地が一緒になって売却できたお話
今回は、土地売却のご依頼から思いがけない展開につながり、無事にご成約に至った体験を、少し専門的な視点も交えてご紹介したいと思います。
ご相談をいただいたのは、以前にお取引をさせていただいたお客様からのご紹介でした。「知人が和歌山市内の土地を売りたいと考えているので相談に乗ってもらえないか」というお話です。
不動産仲介業にとって、過去のお客様からのご紹介は大変ありがたく、また信頼の証でもあります。
現地を拝見すると、土地は道路にしっかり接しており、法令上は建築可能なものでした。ただし、面積が小さく狭小地に該当するため、利用価値や需要の面では制約があると感じました。狭小地は単独では買い手が限られてしまい、価格面でも評価が伸びにくいケースが多いのが実情です。
販売活動を開始し、当事務所で看板を設置したところ、思いがけないご相談をいただきました。
隣地の所有者様から「実は自分の土地も売りたいのだが、接道がないために売りにくい。そちらの狭小地と一緒に売却すれば、接道付きのまとまった土地になるのではないか」というお話です。
ここで少し専門的な解説をすると、「接道義務」は建築基準法第43条に定められています。和歌山市において、建物を建てる土地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。これを満たさない「無接道地」は、再建築ができないため資産価値が大きく下がり、市場での流通性も低くなります。逆に、接道している土地であっても狭小地であれば建物の設計や利用に制約が出るため、これもまた需要が限定されがちです。
ところが、今回のケースでは「狭小だが接道がある土地」と「広いが無接道の土地」が隣接しており、これを一団として販売すれば「接道を確保した十分な広さの土地」として市場に出せることになります。まさに双方の弱点を補い合う関係でした。
もちろん、土地の売却は「そうしましょう」と簡単に進むものではありません。所有者はまったくの赤の他人同士。売却価格の希望も異なりますし、売却スケジュールや条件についても考え方が違います。調整役である私が間に入り、相続関係の確認、測量や境界確定の手配、さらには税務上の注意点など、専門的な課題を一つひとつ整理しながら進める必要がありました。
また、一団の土地として売却するためには「契約を同時に進めること」も重要です。片方だけ先に売れてしまうと全体のバランスが崩れてしまうため、契約・決済のタイミングを慎重に調整しました。
最終的には、双方のご理解とご協力のおかげで「一緒に売却することが一番良い」という共通認識に至り、時間はかかりましたが、無事にまとまった土地として成約に至りました。
今回のケースを振り返ると、不動産取引は「単独の土地をそのまま売る」だけではなく、「隣地や周囲との組み合わせによって新しい価値を生み出す」ことができるということを改めて実感しました。特に和歌山市内のように既存住宅地が多いエリアでは、狭小地や無接道地といった“扱いづらい土地”が多々存在します。そのような土地も、隣接地との調整や専門的な工夫を加えることで市場に適した形に変えられるのです。
不動産仲介業者としては、単に売却を仲介するのではなく、法規制や市場性を踏まえた「最適な出口」を見つけ出すことが求められます。そして、その過程で所有者同士の利害を丁寧に調整し、互いに納得いただける形に導くことこそが、私たちの大切な役割だと感じています。
今回のご縁を通じて、どんな土地にも新しい可能性が眠っていることを強く実感しました。
もし和歌山市や周辺地域で土地や建物の売却をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門的な知識と経験をもとに、皆さまにとって最善の方法をご提案できるよう努めてまいります。